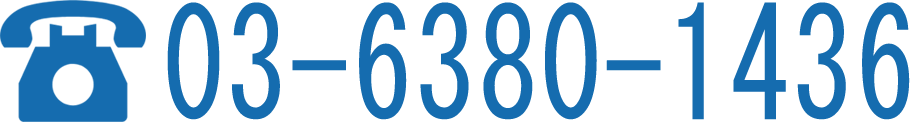デリバティブとは
デリバティブ(derivatives)とは,基本的な金融取引(預金・借入れ,債券,外国為替,株式など)から派生した金融商品の総称です。対象となる金融取引は「原資産」と呼ばれ,原資産の価格変動要因は「リスク・ファクター」と呼ばれます。代表的なリスク・ファクターには,通貨(外国為替),金利,株式,コモディティ(貴金属や原油などの商品)があります。また,原資産に対する経済効果により,先渡し(forward),先物(future),スワップ(swap),オプション(option)などの取引種別があります。日経225オプション取引や,平成20年以前に中小企業に対し山のように勧誘された通貨オプション,クーポンスワップなどが代表例です。
デリバティブ取引の利用目的は,ヘッジ目的(原資産の価格変動リスクの回避・軽減を目的とするもの)と,リスクテイク目的(対象となる原資産の変動を増幅し,積極的に価格変動リスクをとることを目的とするもの)があります。中小企業に販売された商品は(一応)前者の目的,日経225オプション取引は多くの場合後者の目的ということになると思います。
デリバティブ取引には,取引所取引と,店頭デリバティブ取引があります。取引所取引とは,国内外の金融商品取引所を経由する取引で,各取引所の規則により,金額,期間などの取引に必要な諸条件は標準化されています。日経225オプション取引は取引所取引にあたります。一方,相対取引である店頭デリバティブ取引は個別の条件交渉に基づき当事者間で直接契約される取引で,金額,期間をはじめ,取引の自由度が高くなっています。中小企業に対し勧誘された通貨オプションなどは店頭デリバティブ取引にあたります。
多くの中小企業を倒産に追い込んだ商品
平成20年以前に,円安リスク軽減のためと称して,「為替デリバティブ」と呼ばれる外貨の購入を義務付ける契約が,国内の輸入関連の中小企業を相手に,文字どおり「山のように」勧誘され,多くの企業が契約を締結しました(私が目にしたことがあるものだけでも,米ドル,ユーロ,豪ドル,韓国ウォン,ノルウェークローネなどがありました。)。メガバンクのみならず,地方銀行までが,顧客企業に熱心に勧誘を行い,契約を締結させていったのです。
平成20年9月にリーマンショックが起こり,翌月にはその影響が日本に到達しました。円高外貨安が進行し,多くの中小企業が毎月数百万円単位の為替差損を被るに至り,ある企業は倒産し,またある企業は数億円の債務を抱えるに至りました。「円安リスク軽減」目的の商品が,円高時に企業を潰したのです。なぜでしょうか。
為替デリバティブの問題
一番の理由は,「円安時には有利なレートで外貨を買える」ことの引き換えに,「円高時には不利なレートで外貨を買う」ことを義務付けられていたからです。しかも,レバレッジ条件(レシオとも言います)が付されて「不利なレートで『倍の』外貨を買う」という内容になっていたり,ギャップ条件が付されて「『より一層』不利なレートで外貨を買う」という内容になっていたりして,ひとたび円高が進めば莫大な損失を被る商品内容になっていたからでした。
しかも,契約期間が長いものだと10年のものもありました。10年間,一定のレートで外貨の購入を強いられるのです。円高が進行すると,毎月数百万円の損失が発生し,いつまで続くか分からない,契約終了まではまだまだある,という状況に各社が追い込まれました。直ちに解約するという方法も,一応はあります。しかし,解約金は,金融工学に基づき算出される「時価」をベースに決められます。詳しい話は割愛しますが,そもそも金融機関が勧誘してきた為替デリバティブ取引は,契約時点で既に,安いものでは数百万円,通常であれば数千万円,多いものだと数億円のマイナスの時価だったのです。契約を締結すると,即座にこれだけの金額の「含み損」を抱え込むことになります。そして,円高が進行すると,ただでさえマイナスだった時価は,更に大きなマイナスとなります。円高時に解約した企業は,概ね数千万円から億単位の解約清算金を支払いました。
このように,為替デリバティブは,円高が進行すると,毎月数百万円ものお金を支払わなければならず,契約の終わりはまだまだ先の数年後,でも解約するにも数千万円払わなければならず解約もできない,という「地獄」に陥る商品なのでした。金融庁の調査によれば,このような円高時に損失を被る為替デリバティブ契約を中小企業1万9000社が締結していたとのことです。それまで堅実に商売をしてきた会社が,信頼する銀行から勧誘され,やむなく応じただけのたった一つの契約のために,毎月数百万円を支払わされ,倒産の危機に追い込まれたのでした。
なぜ,このような商品を銀行までもが狂ったように勧誘したのか。理由は簡単です。信用取引,外国株式取引,投資信託の項目で述べたのと同じで,理由は,銀行が簡単に収益を上げられるからです。与信審査をして,企業に融資を行い,倒産しないか注視しながら債権管理を行い,ようやく年数%の利息収入をあげる従前のビジネスに比べ,契約させるだけで数百万円ないし数千万円の収益があがる商品なのですから,メガバンクから地方銀行までもが熱心に勧誘したのも頷けます。輸入企業でないにもかかわらず「輸入企業であることにして」販売された例や,円安リスクを負っていないにもかかわらず「円安リスクがあることにして」販売された例もたくさんあります。
被害回復へ向けたこれまでの動き
円高が進行し,為替デリバティブ契約に基づき毎月数百万円の支払いを強いられ,資金がショートし,倒産に追い込まれた会社はたくさんありました。円高倒産企業の3分の1は為替デリバティブが原因であったとも言われています。
契約に基づく資金の受渡しを停止し,金融ADRという方法で被害回復ないし債務の圧縮を図った事案も多くあります。実際にも多くの事件が全国銀行協会やFINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)のあっせん手続に持ち込まれ,解決されました。もちろん,金融ADRではなく,訴訟で損害賠償請求を求める事案もありました。また,中には,あっせん手続で「特別調停案」が出されたものの銀行がこれに応じず訴訟になった例もあります(全銀協の職員の講演録によれば,特別調停案を出したことは過去6件あり,うち2件が訴訟に移行したとのことです。この2件のうち1件は私が担当した事件です。)。もちろん,私自身も,代理人として,金融ADR手続や訴訟を担当し,賠償金の支払いを得たり,債務免除を受けた事案は多数あります。
今後の動き,新たな動き
リーマンショックから相当期間が経過し,為替デリバティブをめぐる状況も様変わりしています。最も顕著なのは,金融ADRへの申立て件数が激減しているということです。一時期,全銀協やFINMACに多くの事件が持ち込まれましたが,現在ではほとんどなくなったと聞きます。これは,おそらく,倒産する企業は既に倒産してしまい,金融ADRで解決できる事案は既に解決され,裁判に移行するものは既に裁判になっているから,であると推測します。不法行為に基づく損害賠償請求の時効が3年であるということも1つの理由にあると思われます。
為替デリバティブにより巨額債務を負担したまま身動きがとれなくなった企業も多くありますが,これを銀行の側から見ると,巨額債権が不良債権化していることを意味します。当然,銀行にとっても時効の問題があるため,為替デリバティブに基づく債権を時効で消滅させるわけにはいきません。この不良債権をどのように処理するのかを注視していたのですが,私が担当した事案の中にも,近時,一部のメガバンクが柔軟な解決に応じてくれている事例が出てきました。また,不良債権をサービサーに債権譲渡し不良債権処理を行う例も見られるようになりました。これにより,サービサーと交渉し,極めて大幅な債務免除を得られた事例も出始めました。反対に,資産を仮差押えした上で,訴訟を提起するという方針をとったメガバンクもありました。また,別のメガバンクが債権者破産の申立てを行ったとの情報も入っています。
このように,銀行によって,また,事案によって,為替デリバティブの「負の遺産」をどのように処理してゆくのかの方針は異なります。これまでのような「取り敢えず全件金融ADRに申立てを行う」というような安直な手続選択は過去のものとなっており,個別具体的事案に応じて,
- (1)金融ADRへの申立てを行う
- (2)訴訟を提起する
- (3)調停・特定調停等の手続で債務免除を求める
- (4)債権譲渡を求める
というスキームを選択する必要が出てきたように思います。私自身も,(1)敢えて今のタイミングで金融ADRへの申立てを行い数億円単位の債務免除を実現した事案,(2)訴訟を提起し和解により解決した事案,(3)調停手続を経て数億円の債務免除を実現した事案,(4)債権譲渡後の譲受債権者と交渉を行い10億円超の債務免除を実現した事案,など,状況や相手方金融機関の態度に応じて,さまざまな手段を講じています。
また,(2)訴訟についても,必ずしも顧客企業にとって良い裁判例ばかりではない中,従前,多く見られた「複雑だから違法だ」という単純な主張立証ではなく,逆に余りに高度・先端的すぎて裁判所が到底採用してくれないような「空中戦」でもなく,地に足をつけつつも,更なる高みにある訴訟戦術を考え,実行していかなければならないと考えます。
当事務所ができること
当事務所には,以上のような,為替デリバティブをめぐる多くの紛争の中で得てきた先端的な経験と知識の蓄積があります。また,金融ADRや訴訟への申立て一辺倒ではなく,「会社を存続させる」「債務を圧縮する」という大きな目標のために最適な手続選択を提案する経験と知識もあり,実際にも,調停の中で多額の債務免除を得た実績や,サービサーとの交渉で9割以上の債務免除を得た実績もあります。ですので,特に,
- (1)取引を中途でストップしたままにしている
- (2)銀行より訴訟を提起された
- (3)債権譲渡され債権回収会社が請求してきている
- (4)解約し,融資を受けて解約清算金を支払った
という近時の企業の状況に即した解決スキームを提案する準備があります。特に,消滅時効を回避するために,銀行は,今後一層,債権回収に乗り出すはずですので,従前(1)の状態で進んできた事案でも,間違いなく,(2)訴訟や,(3)債権譲渡という方法が選択されます。一度,ご相談ください。
また,上記以外にも,証券会社の勧誘により担保付きの為替デリバティブを行ったという事案への対応も可能です。これまでは,銀行の為替デリバティブ取引について多くが語られましたが,証券会社における為替デリバティブ取引についての言説はさほどなかったように思います。しかし,当事務所には,証券会社でのデリバティブ取引に特有の問題性にフォーカスした紛争処理のノウハウもあります。証券会社で担保付きの為替デリバティブ取引を行ってきた場合にも,ご相談ください。
「プット・オプションの売り」という「剥き出しの悪意」(2023年11月更新)
(1) 私とオプション取引との「なれそめ」
オプション取引との出会いは、為替デリバティブ取引がきっかけでした。リーマン・ショック前に、銀行が中小企業に為替デリバティブ取引を狂ったように勧誘しまくり、リーマン・ショックによりリスクが実現化し、多額の損害を発生させました。ある会社については金融ADRで解決し、ある会社については裁判にまで至り、ある会社については特定調停等の中で解決を模索し、ある会社は破産することにもなりました。隔世の感すらありますが、「為替リスクヘッジ」の名の下に、為替ヘッジのニーズをろくに確認もせず、銀行が狂ったように(文字どおり「狂ったように」です)勧誘し、リーマン・ショック後、多額の損害が発生した後には、手のひらを高速で「くるーん」と返して自己責任を声高に主張した、あの様相は、私は今でも忘れていません。
為替デリバティブ取引には、スワップ取引のものもありましたが、多くがオプション取引のものでした。これらの紛争に取り組んでいた時代には、それほど有力な書籍・文献が多くなく、その複雑さ、そのハイリスク性を論述するのには、非常に苦労しました。その後、裁判官らが執筆した「デリバティブ(金融派生商品)の仕組み及び関係訴訟の諸問題」などの書籍が相次いで発刊され、デリバティブ取引は複雑である、ハイリスクである、との理解が広まり、随分と楽になりました。
(2)「オプション取引をいかに隠すか」に腐心する金融機関
オプション取引は、日経225オプション取引のように「私はオプション取引ですよ」と名乗っている取引以外においては、その存在は隠され続けてきました。仕組債が、その典型です。仕組債は、為替・株式・金利などを対象としたスワップやオプションなどのデリバティブ取引を債券に内包させた金融商品です。「債券」の中に、オプション取引を入れて、隠して、見えづらくして、「債券」のラベルを貼って販売されました(仕組債を購入した方の中には、「債券だから安全だと思った」という方が少なくありません。)。
前述したとおり、今では、裁判官らが執筆した書籍に「仕組債は、クーポン(表面利率)を好条件にするために、通常の社債にオプション(顧客から見て売り取引)を組み込んだものである」と断言されているため、「仕組債=デリバティブ取引」「仕組債=オプション取引」という構図を否定されることはなくなりました。しかし、このような有力な書籍や論考がない時代には、金融機関側は、裁判において、「仕組債は単なる債券であり、デリバティブ取引ではない」「債券に複数の条件が付されたものであり、デリバティブ取引とは無関係である」などと主張してきました(誰もが知るメガバンク系の証券会社でも、いけしゃあしゃあと、このような主張をしていました。)。
若干、話は逸れてしまいましたが、以上のように、金融機関は、長年にわたり、「オプション取引の存在をいかに隠すか」に腐心してきたのでした。
(3)「プット・オプションの売り取引の勧誘」という「剥き出しの悪意」
しかし、令和の今、ある証券会社が、「特約権付株券貸借取引」などという取引で、株式のプット・オプションの売り取引を行わせ、巨額の損害を被らせている事案がありました(但し、これは、前述したとおり、「株券貸借取引」に「特約権」を付す、という形をとり、巧妙にプット・オプションの売り取引は隠されていた事案です)。また、これとは別の事案では、顧客に対し、株式のプット・オプションの売り取引を勧誘し巨額の損害を被らせた、という事案もありました。こちらは、まさに、包み隠さず、「生」のオプション取引でした。
私は、とても驚きました。それは、プット・オプションの売り取引を行わせる、という行為に、証券会社の「剥き出しの悪意」を感じたためです。
オプションの売り取引は、前記の裁判官らの書籍においても、「保険料としての実質を持つオプション料を取得して、保険を引き受けるという基本的な性格を有するもの」であり、「オプション料を確定的に取得できる代わりに、原資産価格の変動に伴うキャッシュフローという点では、一方的にリスクだけを引き受けることになる」もので、この利益は「一定額に制限される」が、損失については「理論上無限に拡大する可能性がある」もの、と解説されています。
要するに、オプションの売り取引を行うと、「保険会社」と同じような立場に立つことになり、少額の保険料は確実にもらえるものの、保険事故が起きた場合には、無限大の保険金の支払いを強いられる、ということです。理論上損失無限大のリスクを、少額のオプション料と引き換えに引き受ける、という取引です。得られるオプション料はせいぜい数百万円ですが、損失が発生する場合には、オプション料の数十倍もの損害を被ることもある、という取引です。無論、これらの仕組みを十分に理解した上で、そのような保険事故は起こらないと正確に予測できるならば、「保険会社」の地位に立ち、保険料を受け取る、ということは、あり得なくはないです。しかし、このようなオプション取引の複雑な仕組みや、損益の構造を理解できる方が、それだけいるというのでしょうか。更にいえば、このような取引で顧客側が損をする場合、その損は、そっくりそのまま、取引の相手方である証券会社の利益になります。敢えて悪意を込めて表現すれば、証券会社にとっては、「プット・オプションの売り取引を行わせて、顧客に損をさせれば、短期間で巨額の利益を得られる」「顧客の資産をそっくりそのまま手中に収められる」ということになります。私は、このような性質のプット・オプションの売り取引を勧誘する行為に、証券会社の「顧客の資産を直接吸い上げて利益を得てやる」という「剥き出しの悪意」を感じます。
近年、仕組債についても、このような、「顧客の資産を直接吸い上げて利益を得てやる」という商品が出てきました(仕組債のページの「自社発行・直販される仕組債の“怪”」をご覧下さい)。仕組債でも、「顧客の資産を直接吸い上げて利益を得てやる」という取引が散見されましたが、それと同じか、それ以上に、生々しく、「顧客の資産を直接吸い上げて利益を得てやる」という意図で行われるのが、この、プット・オプションの売り取引です。令和の時代に、再度、生のプット・オプションの売り取引の事案に取り組むことになるとは、全く予想していませんでした。「ここで会ったが百年目」という気持ちです。証券会社に勧誘され、オプション取引を行い、損害を被った場合には、ご相談下さい。